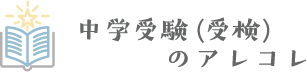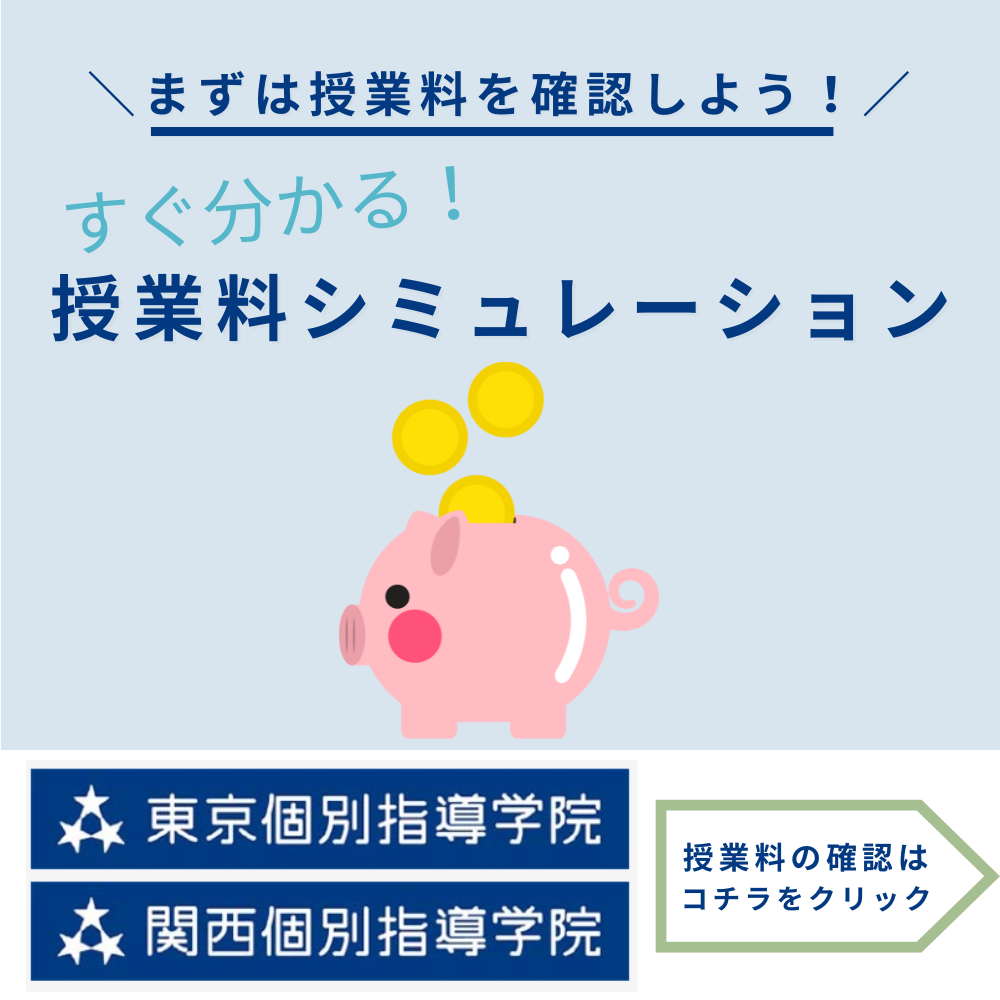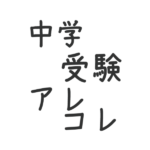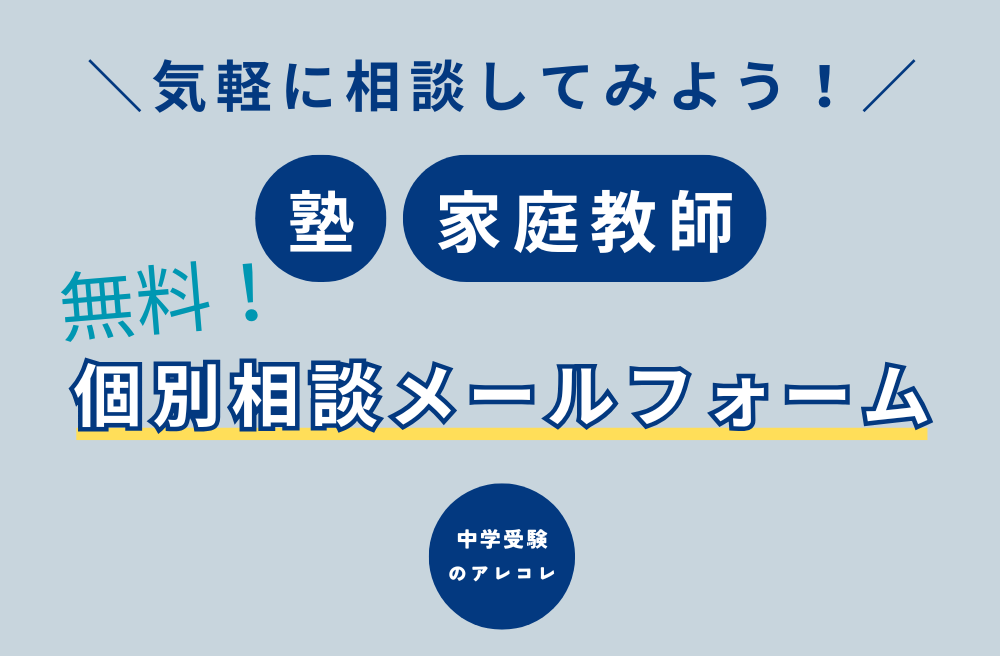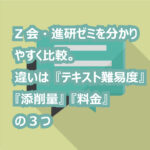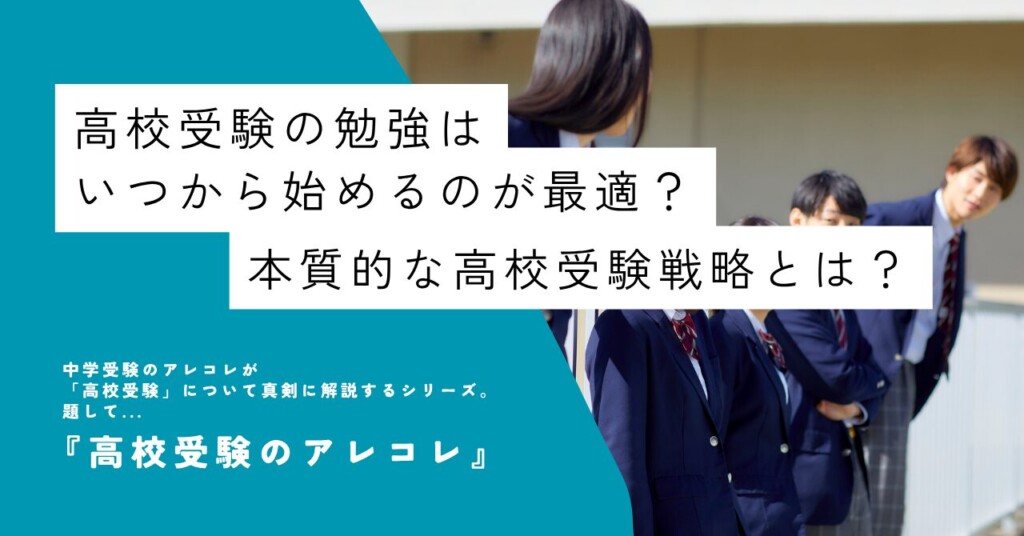
中学生のお子さんを持つ保護者の方であれば、お子さんの高校受験について心配事が多いですよね。
僕のように受験サイトを運営していると
「高校受験の勉強はいつから始めるのが最適ですか?」
と聞かれることが多々あります。
僕は、
- 「受験勉強はしなくていいから普段からコツコツ学校の勉強をしましょう」
と優等生的な答えをしています(なぜ、このように答えるかはこの記事を読んでいただければ理解いただけると思います)。
「受験勉強しなくていいの!?」
そう思われる方もいらっしゃると思いますが、
- 東京で高校受験し
- 大学は国立大・早慶上理などの難関を狙わない。狙ったとしてもGMARCH
という場合は、少し偏っていますが僕の受験戦略では、最後の一年間ガチガチに受験勉強するという感じではなくなります。
では、それは、どのような戦略でしょうか?
これからお子さんの高校受験を控えている保護者の方には参考になると思います。
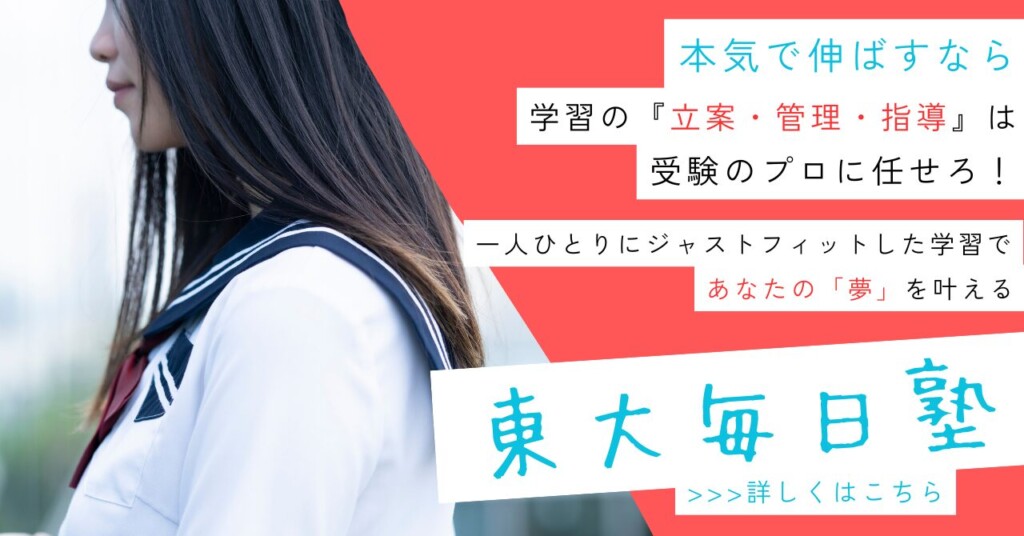
中学受験と高校受験のギャップ
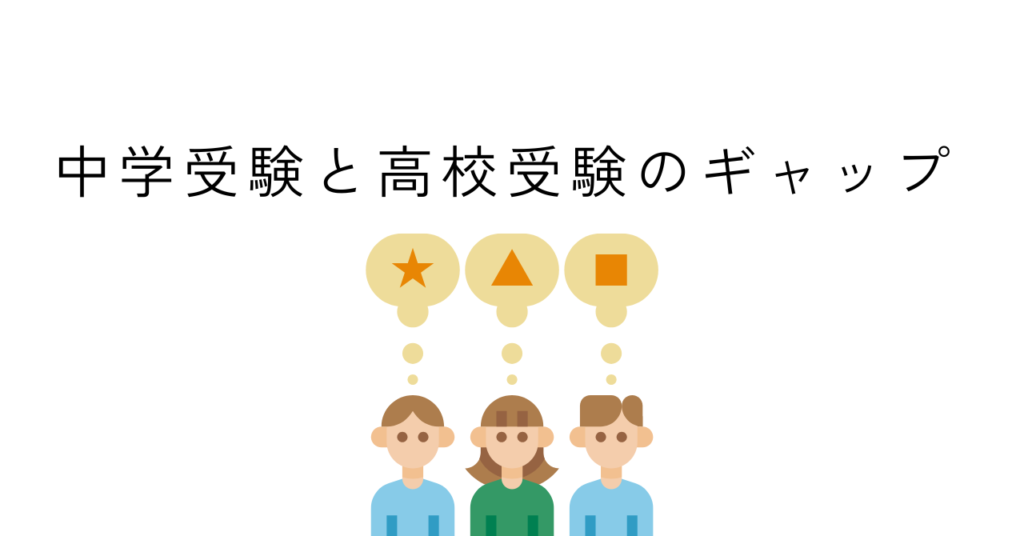
まず「中学受験を考えているご家庭」と「高校受験を考えているご家庭」の「受験」に対する考え方のギャップについて書いていきます。
「中学受験を考えているご家庭」の場合、
- お子さんの「受験」に対し非常に熱心で
- 進学する学校や偏差値にもこだわりがある
ことが多いです。
保護者が熱心なので、中学受験の場合、小学校4年生、早い場合、小学校1~2年生の頃から準備をしているご家庭が多数いらっしゃいます。
特に東京の場合は、人気塾(SAPIXなど)に入塾するため早めに用意するご家庭が多いです。
つまり、受験まで6年間、少なくとも3年間前に準備をするということになります。
これって一般的に考えてメチャメチャ早いですよね。
普通に考えてください。小学校低学年の頃から受験勉強(まぁ、低学年の頃はそこまで実践的な感じではないですが)を進めるってことですから。
小学校入った瞬間に、親は小学校の出口のことを考えているということです。
やはり、それはいい意味で熱心、悪い言い方をすれば狂気的とも言える状況です。
ちょっと早過ぎると言われても仕方ありません。
一方、高校受験を考えているご家庭の場合、特に東京の場合、中学受験をしないご家庭ということですので、それほどお子さんの受験のことを気にしていないご家庭が多いです。
受験のことを考えているご家庭は、中学受験をされます。
中学受験をしていないということは、それほど受験のことを気にしていないということです。
では、高校受験をされるご家庭の場合、いつ頃に高校受験を意識するのか?
僕の経験だと、大体「中学2年の夏を過ぎたあたり」に意識し始め、「中学2年の春休み、3年生になる直前にしっかり対策をし始める」という感じです。
我が家は、長男が中学受験をし、次男が高校受験をするという家庭環境です。
次男が中学1年生に上がってすぐ、次男の通う公立中学校で中学3年生をメインに「高校受験説明会」がありました。
みんな参加するだろうからと、僕も当たり前のように参加したのですが、その会に参加した1年生の保護者は10組程度でした。
長男の中学校の時とのギャップに僕と妻は驚きました。
長男の通っていた中学に限らず、私立中学であれば、ほとんどのご家庭が参加しているでしょう。
- 公立中学は意識が低いからダメとか
- 私立中学の親が学歴にこだわりすぎていてダメとか
良し悪しを言いたいわけではなく、単純に「意識の違いがある」ということが言いたいのです。
そして「先んじれば人を制す」ではありませんが、僕の受験戦略の場合、中学1年生のうちから受験の情報を集めておくことで、他の人と差をつけておけた方が有利と考えます。
- 高校受験の説明会や報告会には積極的に参加する
- 高校の説明会や、学園祭には1年生のうちから参加しておく
- その中から、子供が気になる学校をある程度目星をつけておく
単純に人と違う動きをすることで、良くも悪くも差が生んでおくという考え方です。
僕の推奨する受験戦略であれば、他人には言わず、他人よりも少し早く受験を意識することで最終的に自然な流れで合格を勝ち取っていけるはずです。
「最後の1年でしっかり受験対策(テクニック)をつめこみ、受験を乗り切る」というのはイコール「無理をする」ということです。それは本質的ではないと思います。
「これだけ早く受験に対して意識付けをし、目標が明確になっていて、それに向かって粛々とやっていれば、そりゃ、合格できるわな」という流れを作ることが大切ですし、実際、それが本質的だと考えています。
一般受験にこだわらない
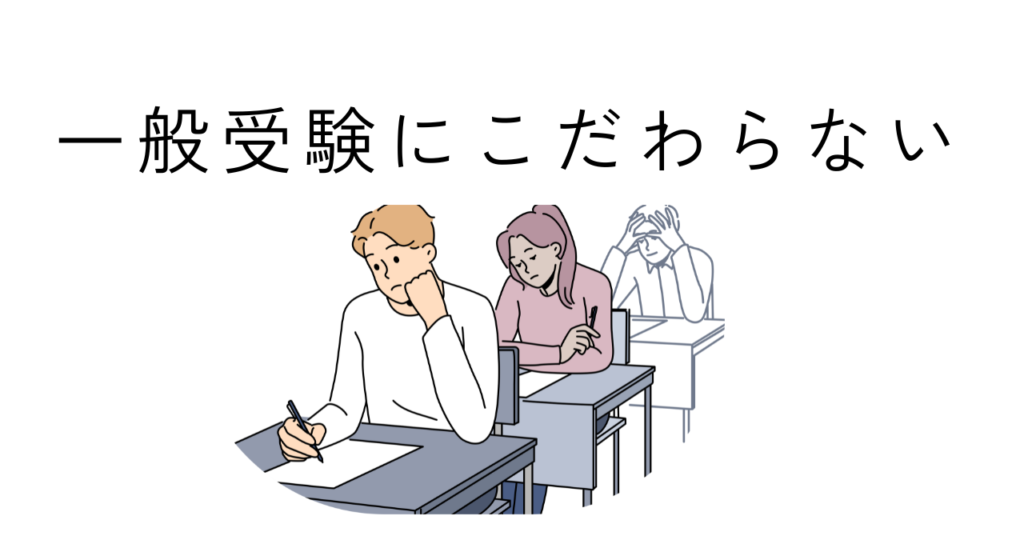
次に『一般受験にこだわらない』ということです。
僕たち親の年代の場合、学歴偏重の社会だったことや、第二次ベビーブームの直後だったこともあり一般受験で苦労した人が多いのではないでしょうか?
特に地方出身の場合は、私立高校も少なく「公立高校こそ神」と教えられ、1人1校しか受験できず精神を削りに削った人も多いことでしょう。
- 一般受験で、しかも一発本番で決めなくてはならない
受験に対し、このようなイメージを持つ人は少なくないと思います。
しかし、現在は状況が違います。特に東京の場合は、一般受験にこだわる必要は全くないのです。
私立高校の数が多い
まずは、私立高校の数が圧倒的に多いということです。
東京に限らず、私立高校が多い地域はどこでも同じことが言えるのですが、公立高校にこだわる必要がありません。
現在は、少子化の影響で、私立校も共学化、進学校化したりと生徒集めに躍起になっています。
完全に「売り手市場」です。
親たち世代が考えているほど、高校受験は熾烈な状況ではないということです。
しかも、東京の場合、中学受験で同級生の20%弱がすでに受験を終了しています。
【中学受験をする割合は?】東京都の私立中学・公立中高一貫校進学率まとめ
そのうえ、私立に進学だとしても助成金が出るので、以前のように「学費の問題で私立高校には行かせられない」ということはないでしょう。(もちろん、私立ならではのプラスアルファの支出はありますが)
公立高校への「一般入試一発本番」ではなく、私立高校進学を念頭に置いておけば学校選択の幅が広がるでしょう。
推薦入試という選択肢
「私立高校進学」を選択肢の一つに加えると「推薦入試」という選択肢の幅ができます。
もちろん公立高校にも推薦入試はありますが、私立の方が間口が広いです。
「内申書だけでない推薦入試」の可能性が出てくるということですね。
例えば、
- 内申書〇〇点以上で、英検準2級を持っている
など特別な活動や実績がなくても(例えば、なにかのスポーツで全国大会優勝など)、学校の求める内容に応じて戦えるようになるということです。
公立と違って私立校の場合、かなり柔軟な対応をしてくれます。
ここだけのウワサ話として読んでもらいたいですが、例えば、
- 私立フェスタなどの説明会に何度も通い、名簿に名前と学校名、塾名を書いておいたりする
とします。
いざ、受験が近づき推薦入試の段階になって、あなたが何度も説明会に参加している学校に願書を提出したとします。
すでに内申点は、その学校の求める水準に達していた場合、学校側はとしてはシンプルに
- 授業を妨害することなくコツコツ日々勉強をしてくれ
- 素行も問題なく、しっかり毎日学校に登校してくれ
- 協調性があり友達と仲良く、前向きで楽しい学校生活を送ってくれる生徒
を望むわけですね。
超有名校、伝統校であれば「特別な何か」を受験生に望むでしょうが、一般の私立校はそこまで特別な何かを望んだりしません。
学校の決めた基準の学力さえあれば、あとは皆と普通に学校生活を送ってくれる生徒を望むわけですね。
非常に保守的に固い判断ですが。
それを知るためにどうするか?
学校側は、これまでの説明会の名簿を開き、
- 名簿に書いてある塾に電話をし、その子の性格などを確認したり、日々の学習への態度を確認したりする
こともあったりします(あくまでウワサ話です.....よ)。
私立校の一担当者が塾に連絡するということです。結構細かい対応をして生徒を選んだりします。
ここまで読んでいただければ、自分の納得できる私立高校の基準までの内申点をとっておき、推薦入試で勝負をした方が良い気がしませんか?
- 「東大合格を目指しているので、当たり前にそういう同級生がいる環境が良い」
- 「どうしても医学部へ入りたい」
- 「名門国立大を目指している」
- 「なんとしてでも早慶に入りたい」
という場合は別ですが、
- そこまで難関大学にへの進学は望まない。できたら日東駒専レベルにいけたら最高
という場合は、あえて一般受験をする必要はないということになります。
一般入試に全てを調整して臨むのと、あらかじめ推薦入試を狙って、コツコツと日頃から無理なく勉強を進めるのでは心持ちが全く違うことは皆さんもお分かりいただけると思います。
ちなみに、実際、次男の通っている塾に確認したところ、ここ数年で私立への推薦入試で不合格だった生徒は一人もいないとのことでした。
皆さんはどう思われますか?
受験勉強はせずに普段からコツコツ勉強をする意味とは?
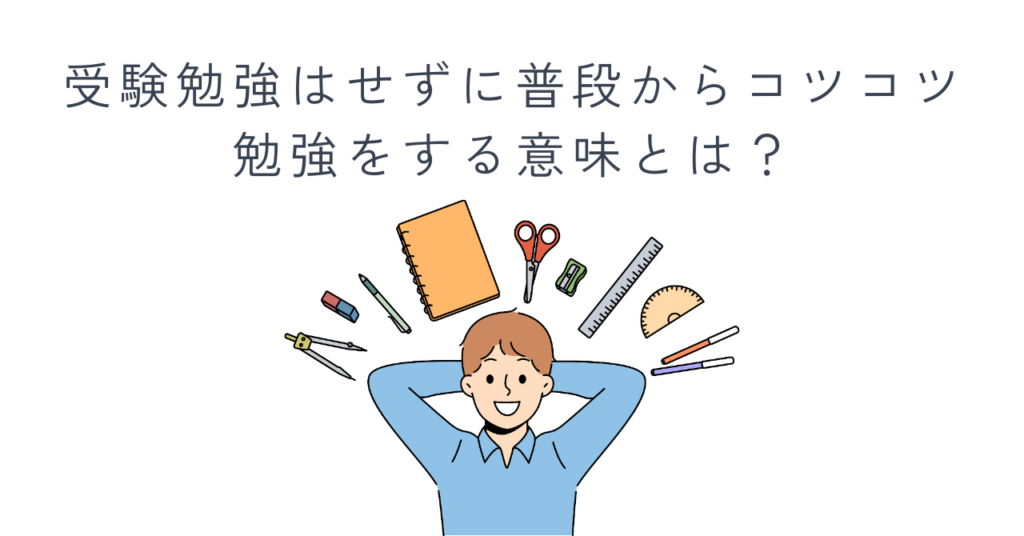
ここまで読んでいただければ、私の考える高校受験戦略のおすすめは、
- 内申点を志望校の定める水準まで達しておくこと
- 私立高校へ推薦入試で進学すること
であることがお分かりいただけると思います。
そのうえ、
- できれば、大学付属校に進学し、大学受験を避けること
をプラスしたいところです。
そのためには、冒頭の一文に戻りますが「受験勉強はしなくていいから普段からコツコツ勉強をする」ことが大事です。
もちろん内申点獲得に、定期テストをしっかり取るためというのは根本にはありますが、それだけではありません。
ここまで熱心に読んでくださったあなたなら理解していただけると思うのですが、
- 受験直前に英検を受験し、準2級を獲得した場合と
- 毎年、コツコツと4級、3級、準2級と獲得した場合と
では、内容が全然違うということなんです。
僕の伝えたいことはそこです。
さらに、漢検・数検は推薦の条件に入ってなかったとしても、もし中1、中2で取っていたとしたらどういう印象になるでしょうか?
- コツコツと努力のできる、日頃から学習する習慣のついているしっかりした生徒
- それをさせているしっかりしたご家庭
- 説明会にも中学一年から参加している熱心な親子
という印象になりませんか?
特に私立の推薦には、そういった積み重ねがとても効いてきます。
面接で口先だけで伝えることは簡単です。しかし、それは誰もがやることです。
それと差別化するためにやってきたことを目の前で一目瞭然と見せることが大切です。
コツコツと積み上げた学習の記録というものは、誰が見ても文句のつけようのない説得力のある資料となります。
だから、僕は、
- 最後の1年で一心不乱に一般受験用の受験勉強を一日15時間もしなくていいから、普段からコツコツ勉強をして、学校側に一目で分かるように検定などに挑戦しゆっくりでいいので獲得しておく
- 中学生らしく部活に励んだり、委員会活動を頑張ったり、中学校生活に前向きに取り組んでいく
- できるだけ休まずに学校に行くようにする
こういう普段の生活を受験時に、学校側に明確に見せることが大切だと思っています。
この方法であれば、受験1年前にいきなり毎日何時間も勉強して偏差値を上げる必要もありません。
日頃の成果を一覧で見せれば良いだけです。簡単ですよね。
内申点も超えていて、これだけ人柄を表現できれば落とされることはまずありません。
コツコツと積み上げていける真面目な子には、とても最適な受験戦略だと思います。
最後に
この記事では、「高校受験の勉強はいつから始めるのが最適か?」という悩みに筆者の考える高校受験戦略を解説しました。
内容を読んでいただければ「なるほど」と思っていただけるのではないかと思います。
東京をメインに解説しましたが、後半は公立校の推薦入試でも同じことですので、やって損はないです。
本文にも書きましたが、我々世代が受験勉強といえば、最後の一年死に物狂いで机にかじりついてライバルより1点も多く点数を削るだすものと考えてしまいがちです。
実際、僕もそのように思っていた人間です(正直、この記事を書いた今でも「本当にこれでいいのか?しっかり対策しなくていいいのか?」と、心のどこかにほんの少しの不安は残っています)。
しかし、そのマインドブロックを外し、我々の時は状況が全く変わっていることをしっかり認識しておく必要があるでしょう。
この急速な少子化を考えれば、我々の時と同じ数の学校数で生徒の受け入れができないわけがないのです。
もちろん前述のとおり、あきらかに難関校である場合、皆「できたら進学したい」でしょうから倍率が高くなり、しっかり対策しなくてはいけなくなるでしょうが、「そこまでは求めない」という場合、今回紹介したような考え方の方が、お子さんの時間を有意義に「本当にやりたいこと」に使わせてあげられると個人的には思います。
記事を読んだだけで心配な場合は、ぜひ一度私立フェスタなどに参加し、高校の担当者に直接たずねてみることをおすすめします。