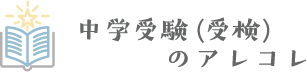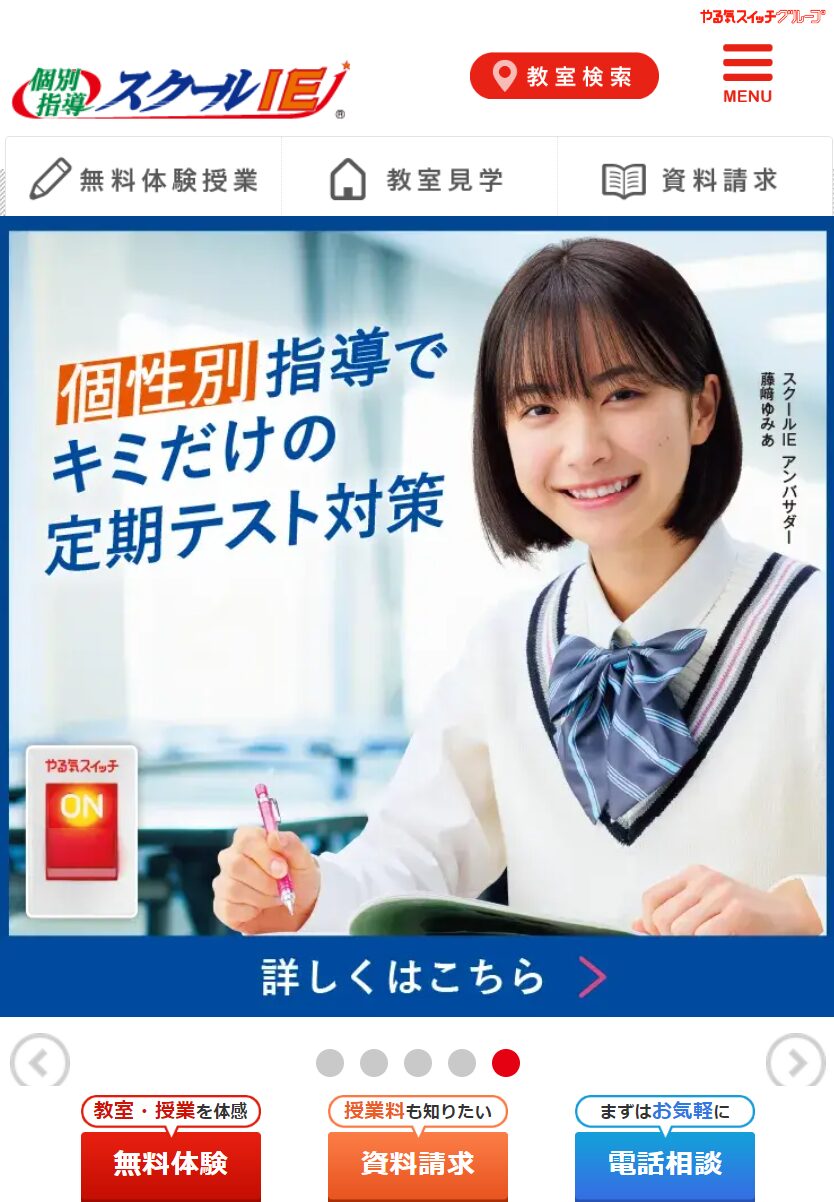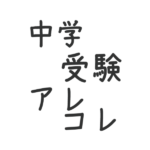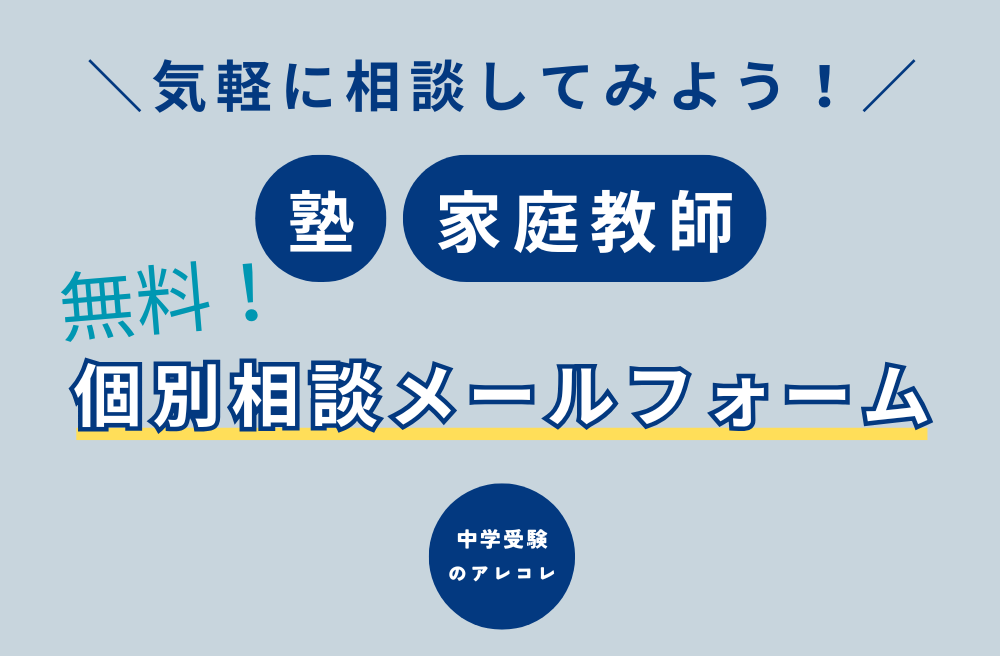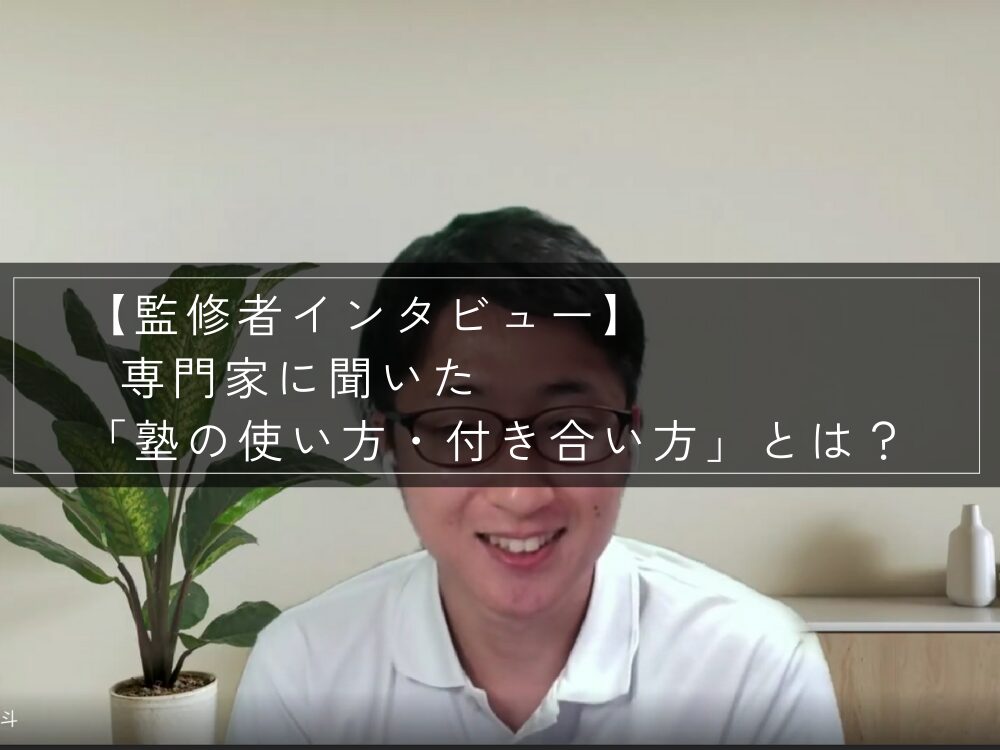
- 「塾に入っているけど、どうも成績が上がらない」
- 「我が子の性格に塾が合っていない感じがする」
「塾との付き合い方」は、どのご家庭でも一度は考えてしまう悩みですよね。
そこで、このサイトの監修をしていただいている東大毎日塾の内田代表に「塾の使い方・付き合い方」など、いくつかお聞きしました。
塾経営者・教育者目線のとても勉強になる内容ですので、お子さんの受験や塾選びの情報収集をされている方には参考になると思います。
この記事を読んでわかること
- 専門家に聞いた「塾の使い方・付き合い方」とは?
もくじ
【監修者インタビュー】「塾の使い方・付き合い方」とは?

このサイトの監修をしていただいている東大毎日塾の内田代表にオンラインでインタビューをさせていただきました。
その中で「塾の使い方・付き合い方」について、塾経営者・教育者目線の参考になるお話をお聞きできましたので、できるだけインタビュー原文そのままに文字おこししていきます。
個別指導塾・家庭教師の利用方法
(リョウスケ)「集団塾と個別指導塾があって、中学受験の場合はやっぱり集団塾に行くことが多いじゃないですか。」
(内田)「はい。」
(リョウスケ)「それで、個別指導塾や家庭教師の使い方っていうのと、やっぱり『スポット利用』みたいな感じで使われてることが多いと勝手に思っているんですよね」
(内田)「ええ、ええ」
(リョウスケ)「ただ『思考停止で集団塾を使う。個別指導塾、家庭教師はスポット利用』ってのは違うかなと思っていて、やっぱり子供の性格や状況によって変わってくるっていうか。そこらへんは、塾を運営されてる内田さん目線で『どういう風に使うのがいいのか。こういうふうに使ってみたらどうですか?』っていうようなアドバイスみたいなのってありますか?」
(内田)「ああ、なるほど。個別指導塾とか家庭教師は結構スポット的に、そのコマを取って授業をしてもらって、特定の科目を教えてもらうっていう使い方になると思うので、苦手な科目が明確になっていて『これを教えてほしいです』っていうのが明確な人が使うと効果出しやすいんじゃないかなと思います。逆に『そもそも何からやればいいか分からないとか、どうやればいいか分からない』みたいな人は、個別指導塾とか家庭教師じゃなくて、学習管理型のコーチング塾。東大毎日塾とかもそうですし、うちの塾以外にもいっぱいあるんですけど、塾側が、ちゃんと現状分析して計画立ててくれて、その進捗確認、定着度のチェックまでやってくれて、手厚くまるっと見てくれる、そういう塾の方がおすすめです。」
(リョウスケ)「なるほど。
- 『これ教えて欲しいです』と苦手科目が明確な場合は個別指導塾
- 『何からやればいいか分からない、どうやればいいか分からない』という子は学習管理型のコーチング塾
が良いだろうということですね。」
コーチング塾を利用するタイミングは?
(リョウスケ)「指導方法もそうなんですけど、年齢によっても『やっぱりコーチングしていった方がいい』とか『集団塾で板書みたいな形でやらせた方がいい』とかってあるじゃないですか。内田さんとしては『コーチングに切り替えた方がいいよ』っていうのは、何歳ぐらいとか、このタイミングからとか明確にありますか?」
(内田)「そうですね。明確に『何歳で』とか言えないですが、『元をちゃんと取ろう』みたいな考え方ではなくて、『あまり予算を気にせずに必要な授業を必要な人から受けられればそれでいい』みたいなご家庭であれば、なるべく早い段階から学習管理型のコーチング塾に行っちゃった方が、自立してやるべきことを一緒に考えたり、勉強法から教えてもらえたりするのでプラスにはなるんですよ。ただどうしてもそういう塾って本人がやるかやらないかも当然大きくなってくるので、特にオンライン塾だと、生徒からなかなか質問しておらず、うまく使いこなせないなっていうことが多いんですよ。そこをもったいないと感じちゃう人は、特に小学生とか低学年のときは、もう授業主体の塾にしちゃった方が、金額に対してやってもらうことがすごく分かりやすいので、納得感は得やすいかなと思います。」
(リョウスケ)「なるほど。本人の年齢とかっていうより本人の取り組み方次第、自覚次第ってことですよね。』
オンライン家庭教師、派遣型の家庭教師、どっちがいい?
(リョウスケ)「オンラインの塾って、私も子供に使わせてたんですけど、やっぱり小学生ってなかなか自分から質問を表現するのが下手くそで。」
(内田)「あ、そうですね。」
(リョウスケ)「そうですよね。だからなかなかそこらへんが難しいかなと思ってたんですけど、実際には、次第に慣れてきてやれるようになって、案外、慣れるもんだなぁってのがあるんですよね。今後、小さい頃から使っていくならオンラインに慣れさせた方が将来的には便利だなぁと。実際のところ、オンラインと実際の派遣型の家庭教師と個別指導塾、その辺の選び方って何かありますかね。」
(内田)「リアルな家庭教師とオンラインの個別指導塾の選び方ですね。直接オフラインで話した方が集中して聞ける子っていると思うんですよ。逆にオンラインだともう全然集中できないみたいな子も小学生とか低学年だといるかなと思うんですけど、そういう子であれば、もう対面のほうが、家庭教師でも個別指導塾でも、対面の方が結果は出やすいんじゃないかなと思います。逆にもうデジタルネイティブ世代で、普通に友達ともチャットで話したり、オンラインビデオ通話で話すような子は慣れてると思うんで、全然オンラインでも大丈夫だと思います。使い分けはそういう考え方でいくといいんじゃないかなと思いますね。」
(リョウスケ)「なるほど。無理をすることないけど、今どきの子はオンラインに慣れてますものね。利便性を考えた場合、オンラインですよね。断然」
状況を素直に伝えられ、言われたことを素直にきいて実行できる子は伸びる
(リョウスケ)「現在、御社の場合は中学生からですよね?」
(内田)「大学受験生、高校生がメインなんですけど、中学生もいますね。」
(リョウスケ)「御社の、うちをこういう風に使ってもらえたら効果が出やすいですよっていう利用方法みたいなものってありますか?」
(内田)「ああ、そうですね。今の自分の状況、困ってることとかをちゃんと教えてくれると、すごく効果は上げやすいですね。例えば、今、学校でこういうこと習ってるんだけどここが苦手とか、この教材が学校指定で使わされてるんだけど、どうも使いにくくて困ってるとか、そういう状況を伝えてもらえると、それだったらじゃあちょっとこっちの教材を追加しようとか、結構いろんなアドバイスができるので。自分の状況をちゃんと伝えてくれると、すごく指導はしやすいし効果も上げやすいですね。ただ実際、それを目指してもそれができる子ってあんまりいません。結局口下手というか、なかなかうまく伝えられない子の方が多いので、そこはこっちからヒアリングしていくので心配しないでください。目指すところは、ちゃんと自分のことを伝えるっていうのをやってもらえるといいかなと思います。」
(リョウスケ)「今、御社で効果を上げてる子の特徴って何かありますか?」
(内田)「それはもう素直に言われたことを全部やる子ですね。すごく上げやすいです。任せてくれる子は。」
(リョウスケ)「ああ。」
(内田)「どんな塾でもそうかなと思うんですけど、素直な子はやっぱり伸びやすいです。言われたことを全部やるみたいな。逆になんか変にひねくれてて、言われたことをやらずにもっとこっちの方がいいんじゃないかなとか、色々考えた結果なかなか行動しないとか、そういう子は当然伸びにくくなっちゃいますね。」
今はコンテンツが充実しているので、それをどう使っていくかが重要
(リョウスケ)「結果の良かった子っていうのは、東大毎日塾さんだけを使われてます?それとも他の集団塾とダブルスクールみたいな感じですか?」
(内田)「たまに併用している人もいますが、東大毎日塾だけを使ってる人の方が多いですね。まず、なんで東大毎日塾だけでいけるかっていうと、基本的に今って、予備校の先生が参考書とか問題集とか執筆してて、めちゃくちゃ分かりやすい教材が増えてるんですよ。スタディサプリみたいに映像授業もめちゃくちゃ分かりやすい。そんな風にコンテンツは本当に充実してて、あとはもうどのコンテンツを選択して、いつまでにどうやっていくかを明確にして、ちゃんとそれをやりきっていくってことができれば成績上がるので、もう全然うちの塾だけで問題ないです。ただ、たまに、予備校のこの夏期講習を受けたいとか、ちょっとこの先生の授業は予備校の方で受けたいからっていう形で、コンテンツの1つとして予備校の授業を使っていくって人もいます」
(リョウスケ)「なるほど。今の時代、あえて集団塾でティーチングしてもらわなくても良いコンテンツ(教材)が数多くあるから、それを『やりきっていく方法を教えてもらったり』『やり切れるように管理してもらったり』することが重要ってことですね」
東大毎日塾のようなコーチング塾が選ばれる理由は?
(リョウスケ)「失礼な話ですが、親目線で考えると、やっぱりなんだかんだで大手の塾、集団塾っていうのを我々は意識しちゃうもんで。」
(内田)「はいはい、そうですよね。やっぱりどうしても安心ですものね」
(リョウスケ)「そうそう、そうなんですよ。ただ、それでもやっぱり、そうじゃなくて御社が選ばれてるっていうのは、なんでだと思われます?」
(内田)「やっぱりそういうところ使っても、なかなか成績が上がらなかったっていう経験から、『ちょっとこのまま行ってもしょうがないな』っていうのが子供にも親にもあるんだと思います。やっぱり中学生だと割と一般的な集団塾使う人多いかなと思うんですけど、なかなかそれで思うようにいかなかったっていう経験をしてる人もやっぱり多くて。偏差値で言うと、高校受験で偏差値50いかないぐらいとか、55いかないぐらいっていう子が多いんですけど、やっぱりその経験則があるので、これちょっと授業を受けてるだけじゃまずいなっていう感覚が、やっぱりもう全体として芽生えてきてる。なので、やっぱり学習管理型のコーチング塾で、やり方から全部教わって、やることも明確にしてもらって、あとはちゃんと進捗確認とかもしてもらって、『ちゃんとやらなきゃ当然ダメだよね』っていうことが、もうみんな分かってきたので、うちの塾とか、学習管理型のコーチング塾を使う人は増えてるのかなと思います。」
(リョウスケ)「やりっぱなしになってしまうから、やっぱり管理までしてもらった方が、まあ親的にも楽だし、本人も楽。」
(内田)「そうです。」
(リョウスケ)「自分で計画を考えなくてもいいから。難しいのは計画ですからね。答えもないですし。計画を立ててもらってやりきればいいっていうことですね。勉強だけに集中すればいいっていうか」
(内田)「そうですね。で、実際多分、業界としてそういう塾めちゃくちゃ増えてて、ライバルも増えてるんですけど、市場全体としては、お客さんも増えてるんですよ。予備校とか従来型の塾とかから、徐々に流れてきてるので、全体のトレンドとしては、学習管理型のコーチング塾って今すごい伸びてるし、結構求めてる人も多いんだろうなっていうのは感じてます。」
東大毎日塾の場合、1年間あれば偏差値10ぐらい上がるっていうのは普通にある
(リョウスケ)「御社の場合、ボリュームゾーンは偏差値どのくらいの子が多いんですか?」
(内田)「これも色々なんですよね。別に全然東大志望限定の塾とかではないので。まあ、偏差値40ぐらいから偏差値60ぐらいがボリュームゾーンになりますかね。幅広すぎますけど。『この層だけがとても多い』ってのはあんまりなくて、結構幅広いです。」
(リョウスケ)「なるほど。その、まぁとても下世話な話で言いづらい部分もあると思うんですが、どんっ!と、(成績を)上げる自信はありますか? 笑」
(内田)「あります、あります(笑)。あの、ただスピード感というか、期間との兼ね合いなんですけど、1年間あれば偏差値10ぐらい上がるっていうのはもう全然うちの塾だと普通にあるので。そこは普通にあり得る数字で。逆に、1年間で偏差値20以上っていうのは、もう相当レアケースでうちの塾ではほぼありません。だから、そのくらいを求めてると『期待と違うな』っていう感じになっちゃうと思います。まあ、たぶん、どこの塾もそうかなと思うんですけど、短期間で20、30上げるってのは相当難しいと思います。」
(リョウスケ)「(20、30は)難しいですよね、それはね。なるほど。塾生の皆さんの最終的な出口は、第1志望に行かれてる方が多いんですか?」
(内田)「多いですね。数字的には、累計で37%が第1志望校合格率なんですけど、去年、2024年度に関しては52%だったんですよ。で、たぶんこれ結構、業界の平均と比べると多くて、一般的に大学受験の第1志望校合格率って10%ぐらいって言われてるので、だいたいその4、5倍ぐらいの数字になってて、結構多分多い方だと思います。」
東大毎日塾を選ぶのは親?子供?
(リョウスケ)「52%はスゴイですよね。なるほど。その実績ですと、御社を選ばれるのってやっぱ親御さんが多いですか?」
(内田)「そうですね。多いです。」
(リョウスケ)「子供が自ら『ぜひとも指導してもらいたい』ってことってのは少ないですかね。」
(内田)「あの、実は両方あるんですよ。御社『中学受験のアレコレ』さんみたいにGoogle検索で結構上位に来る記事からの流入の場合は、割と親が調べることが多いんですけど。ウチ勉強法系のブログとかSNSもやってて、そっちからは結構生徒が調べてくることもあります。」
(リョウスケ)「なるほど。そうか。でも、まあそうですね、私見ですが、これからは、やっぱり、コーチング塾の方が成果を上げやすいと思っています。オンラインの英会話とかもそうですけど、やっぱり、なんだかんだで英会話で会話だけしてても全然、英会話力が上がらなくて、英語コーチングで管理指導してもらった方がやっぱり最終的に成果が出るっていうケースが多いですもんね」
(内田)「そうです」
(リョウスケ)「管理型の塾の方が主流になるのかもしれないですね。」
(内田)「だと思います。ていうか、たぶん、これ大人でもそうだと思うんですけど、ライザップがあれだけ流行ってるのって自分でできないからだし。やることも、まあ何が自分に合ってるのか分からないっていうのもあると思うんですけど。YouTubeとかで調べれば情報ってたくさん出てくるんですけど、ダイエットも勉強法も。ただ自分に合ったやり方って何だろうっていうのがやっぱみんな分かってないんで、そこをやっぱ明確にしてもらいたいっていうニーズは、すごいあるんだと思いますね。まあ、加えてやっぱダイエットも勉強もサボっちゃう人すごく多いので、たまにじゃなくて毎日管理してもらいたいっていうニーズはすごくあるんじゃないかなと思いますね。」
東大毎日塾、今後の展開は?
(リョウスケ)「東大毎日塾さんの今後の展開としては、例えばオンラインじゃなくてオフラインの塾を作るとか、色々こう展望はございますか?」
(内田)「そうですね、現状オフラインの塾を作ろうっていうのは今のところは考えてなくて、オンラインに特化してやっていこうと思ってて。今進めてるのが、通信制の高校と提携して、その高校のコースの1つとしてうちの塾が指導するっていうことはやってるんですけど。」
(リョウスケ)「今、やられてるんですね。」
(内田)「そうですね。これは結構、手応えは感じてて、学校でここまで密な指導を受けられるって、やっぱりかなり珍しいので。でも求めてる人はすごく多い。だからこそ、みんな塾に通うんですけど。それなら学校で、それをできちゃった方が絶対いいので。もうちょっと広げていけたらいいなぁとは感じてますね。」
一般受験だけでなく、指定校推薦・総合型選抜の対策も可能
(リョウスケ)「御社の場合、基本的には一般入試で合格させることを前提で指導を考えられてるんですか?」
(内田)「あ、実は両方ですね。一般入試と総合型選抜と。あと指定校推薦とかもあるんですけど。全部考えてます。」
(リョウスケ)「ああ。総合型選抜の対策も御社でできると?」
(内田)「そうですね、やってます。今って結構、総合型選抜入試増えてるので。」
(リョウスケ)「そうなんですよね。」
(内田)「そこもやっていかないと、生き残れない時代になってる気はします。」
(リョウスケ)「ですね。ほとんどが推薦みたいな学校も多いですしね。」
(内田)「ええ。総合型選抜とか推薦専門の塾もあるんですけど、専門でやっちゃうと総合型選抜って、こけた時にちゃんと一般に切り替える必要もあるので、まあ絶対共通テストの勉強はしておかなきゃいけなかったりとか、普通に日頃の勉強をちゃんとしておく必要があるので、やっぱ両方ハイブリッドでやっていくのは必要だなと思ってますね。」
(リョウスケ)「なるほど。いやぁ、すごい。両方やられてるとは。私も子供の大学受験を通してよく分かりましたが、なんかもう『正々堂々と一般入試で』と侍のようにやっていても、やっぱり厳しいなって。」
(内田)「そうです。」
(リョウスケ)「特に東京で入試をやるんだったら、特に高校入試に関してはそうですけど、もう断然、推薦取っといた方が良い。」
(内田)「ええ。」
(リョウスケ)「絶対にてっとり早いなというか。使えるものは何でも使っていかなきゃダメだな、というふうには思っていて。そこらへんの対策を今後やっぱり塾としてはやっていかないとダメだよなぁと思ってたので。」
(内田)「そうですね。」
高校受験から継続して利用してもらいたい
(リョウスケ)「基本的には大学受験がメインということなので、中学生に対しての指導って今後は考えられてるんですか?増やしていきたいとか。」
(内田)「ああ、そうですね。そこは考えてるんですけど、じゃあ、具体的に、経営の方針として、今すぐそこに集客の窓口を広げていこうとかはあんまり考えてなくて、まず大学受験の方を優先しちゃってますね、今は。でも、実際の指導のこと考えたら絶対早くから指導した方がいいので。もっと東大毎日塾が周知されるようにしていきたいなと思ってます。」
(リョウスケ)「たしかにそうですよね。高校受験で中学生を塾生として迎え入れて、ずっとそのまま継続的に大学受験まで行ってもらった方がいいわけですもんね。」
(内田)「絶対その方が伸びますし、まあ経営的にも絶対安定しますし。目指したい所ではあります。」
(リョウスケ)「うーん、なるほど。継続することによって、成績も伸ばしていきやすいし、塾側としてもメリットがあるということですね。今後の東大毎日塾の展開を期待しています。本日はありがとうございました」
(内田)「ありがとうございました」
最後に
この記事では、このサイトの監修をしていただいている東大毎日塾の内田代表に「塾の使い方・付き合い方」など、いくつかお聞きしました。
塾との付き合い方は、お子さんの性格によって違います。
受験には制限時間があります。
思考停止で集団塾を選択するのではなく、しっかり選んでいきたいですね。