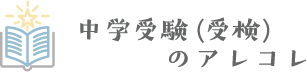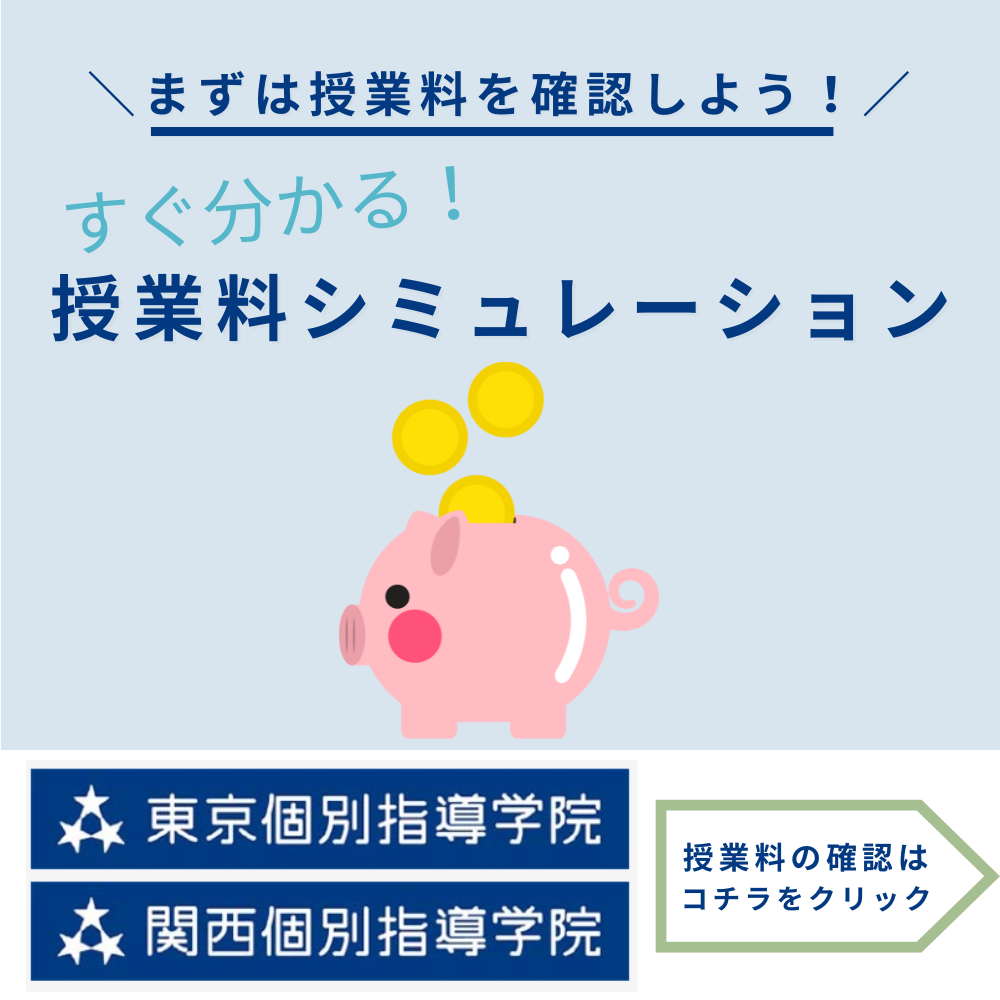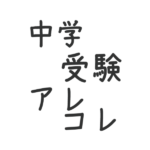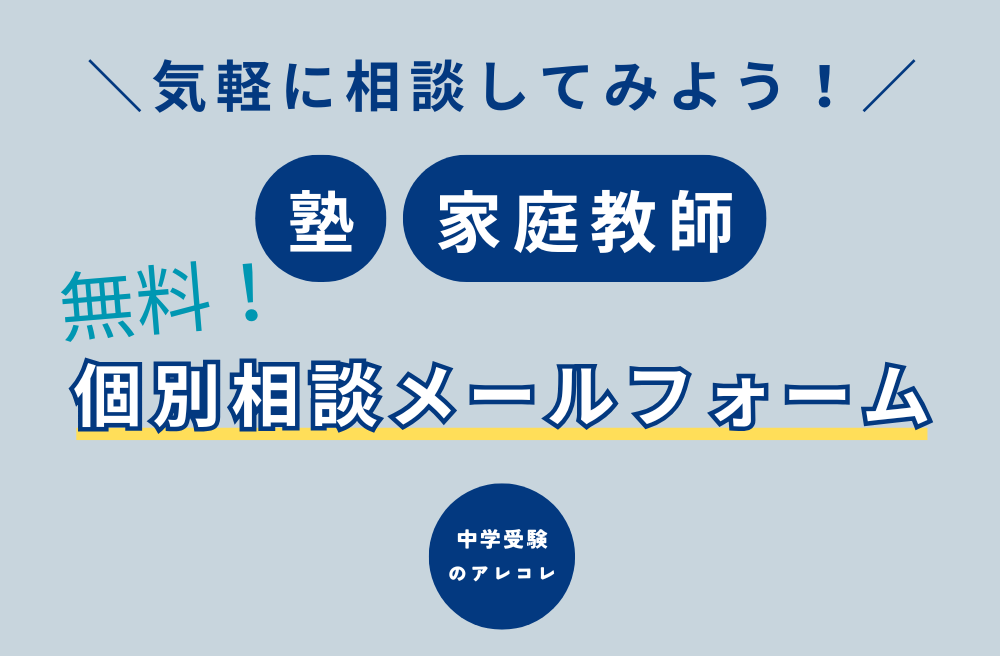受験の準備を始めようと思った時「何から始めればいいのか?」と悩むご家庭は少なくありません。
- 塾に入り勉強しつつ情報を集める
- 参考書を買う
- 模試を受ける
多くの方が迷うところですが、結論から言うと、
- まずは「私学フェスタ」や「合同学校説明会」に足を運ぶこと
がもっとも大事です。
「えっ!?なんで?」と意外に感じる人も多いでしょう。
「なぜ、まず説明会に参加した方がいいのか?」
この記事では、受験サイトを10年以上運営し、この界隈に精通している筆者が詳しく解説していきます。
この記事を読んでわかること
- なぜ、まず説明会に参加した方がいいのか?具体的に説明していきます。
もくじ
受験勉強は何からすればいい?まずは、私学フェスタ・合同学校説明会に行こう!

なぜ、まず合同学校説明会に参加するのか?
なぜなら、合同学校説明会に参加することでお子さんが、第一印象で何か惹きつけられる学校に出会えるからです。
例えば、
- 文化祭が楽しそう
- 独自の行事がある
- 憧れの部活がある
- 制服が可愛い/制服がない…
など、なにかしら「“好き”の芽」が見つかります。
これは、これから始まる長丁場の受験に不可欠な「燃料」となります。
学校合同説明会(私学フェスタ)の魅力は、複数の学校を一度に比較できることです。
校風や制服、部活動、行事、進学実績などを実際に見聞きすることで、パンフレットだけでは分からないリアルな雰囲気を体感できます。
どの学校も自校の魅力を伝えられるよう工夫を凝らして参加しています。
そのうえ、ランダムに一校選んで説明会に行くよりも、合同説明会の方が多くの学校で出会えます。
お子さんの「心に引っかかる」学校に出会える確率が高くなります。
別に仮でもいいのです。
少し気になる「目標となる」学校を見つけることが大事です。
お子さん自身が「ここ楽しそう!」と感じるポイントを見つけられるかどうかは、その後の受験モチベーションを大きく左右します。
受験勉強の第一歩は「勉強」ではなく「学校を知ること」。
お子さんにとって「行きたい」と思える学校を見つけることが、受験を成功させるための最初のカギです。
また、目標となる学校を見つけることには、もう一つ大事な理由があります。
なぜ目標となる学校を見つけることが大事なのか?

仮でもいいので目標となる学校を見つけることが、受験勉強の第一歩であり最大のポイントです。
なぜなら、目標を定めることで
- 「勉強の方向性」
- 「必要な努力の量」
が明確になるからです。
- 目標とする学校の合格基準レベル(偏差値)- 現在の自分の学力(偏差値)=埋めるべき差分
受験勉強とは、この「差分」を埋めていく作業です。
例えば、何となく塾に通って勉強していても、どのレベルを目指すのかが曖昧だと、学習の進度や強化すべき科目も曖昧になります。
結果として、時間も費用も無駄になってしまうケースは少なくありません。
逆に、志望校を仮にでも設定すると、そこに必要な学力水準(偏差値や内申点、検定レベルなど)が数字として見えてきます。
そして、お子さん(自分)の現在の学力との差分を把握することで
- 「あと、どれだけ力をつければいいのか」
が明確になります。
例えば、中学受験なら四谷大塚の合不合判定テストや首都圏模試、日能研全国模試などの公開模試。
高校受験ならV模擬やW模試などの結果を参考にして、志望校偏差値との差を見ます。
この差分がそのまま、これからの受験勉強の道しるべになるのです。
つまり、目標校を持つことは「地図を持つ」こと。
地図がなければどの道を進めばいいのか分からないように、志望校がなければ勉強の優先順位も決まりません。
だからこそ、最初のステップで「少しでも気になる学校」を見つけることが極めて大切なのです。
差分をどうやって埋めるのか?
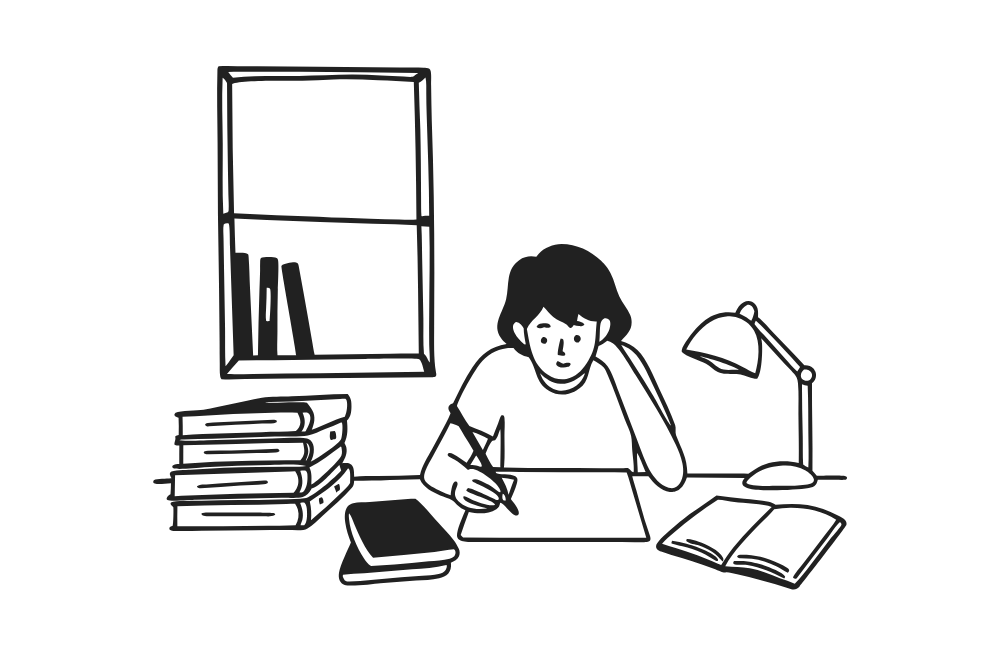
ザックリでいいので、志望校と現在の学力の差分が分かったら、次に考えるべきは「その差分をどう埋めるのか」です。
受験勉強とは、
- この差分を一つひとつ埋めていく作業
に他なりません(逆にすでに差分が無い場合は、ガッツリと受験勉強をする必要はないということになります)。
差分を埋める方法は、大きく分けて次の2つです。
- 自力で勉強する(参考書や家庭学習中心)
- 塾や家庭教師など、外部の力を借りる
どちらを選ぶべきかは、差分の大きさと残された時間によって変わります。
ここを論理的に判断することで、無駄なく最短距離で目標校に近づけるのです。
偏差値の差分が10以内で、受験まで1~2年ある場合
偏差値の差分が10以内で、受験まで1~2年ある場合は、
- 大手集団塾
に通うのが一般的な進め方です。
大手塾のカリキュラムは体系的に設計されており、基礎から応用まで段階的に積み上げることができます。
まだ時間に余裕があるため、集団授業で全体的な底上げを狙うのが合理的です。
ただし、性格的に集団塾が合わないお子さんの場合は、個別指導塾や家庭教師といった選択肢も検討した方が良いでしょう。
このサイトでは、いつも書いていますが、成績を伸ばすにはお子さんの性格にあった塾の形態を選ぶ事が大事です。
偏差値の差分が10以内で、受験まで1年未満の場合
残された時間が短い場合は、
- 大手塾+個別指導(または家庭教師)
という組み合わせで集中的にテコ入れすることが効果的です。
大手塾で全体の学力を維持・底上げしつつ、個別や家庭教師で弱点をピンポイントに補強する形です。
特に過去問演習や志望校特有の出題傾向に対応するには、個別のサポートが強力です。
偏差値の差分が10以上ある場合
偏差値の差分が10以上ある場合、単に授業を受けるだけでは間に合いません。
必要なのは学習の習慣化と進捗管理です。
そのため、学習コーチング塾や計画・管理を重視する指導スタイルが向いています。
中学受験ではコーチング塾は少ないため、個別指導を厚めに入れつつ、家庭でもスケジュール管理を徹底するのが現実的です。
すでに目標水準に達している場合
逆に、すでに志望校の基準に届いている場合は、必ずしも塾に通う必要はありません。
学校の授業をしっかり理解しつつ、過去問を使って志望校の傾向に合わせた対策を進めれば十分です。
必要に応じて、弱点だけを補強するために家庭教師や個別指導をスポットで利用するのも有効です。
このように、差分の大きさと残り時間によって、最適な勉強法・塾のタイプは変わります。
- 「なんとなく近いから」
- 「友達が通っているから」
- 「大手だから」
という理由で塾を選ぶのではなく、差分を基準に論理的に判断することが、受験勉強を効率的に進めるカギと言えます。
塾選びの判断基準(距離・費用・対応学年など)
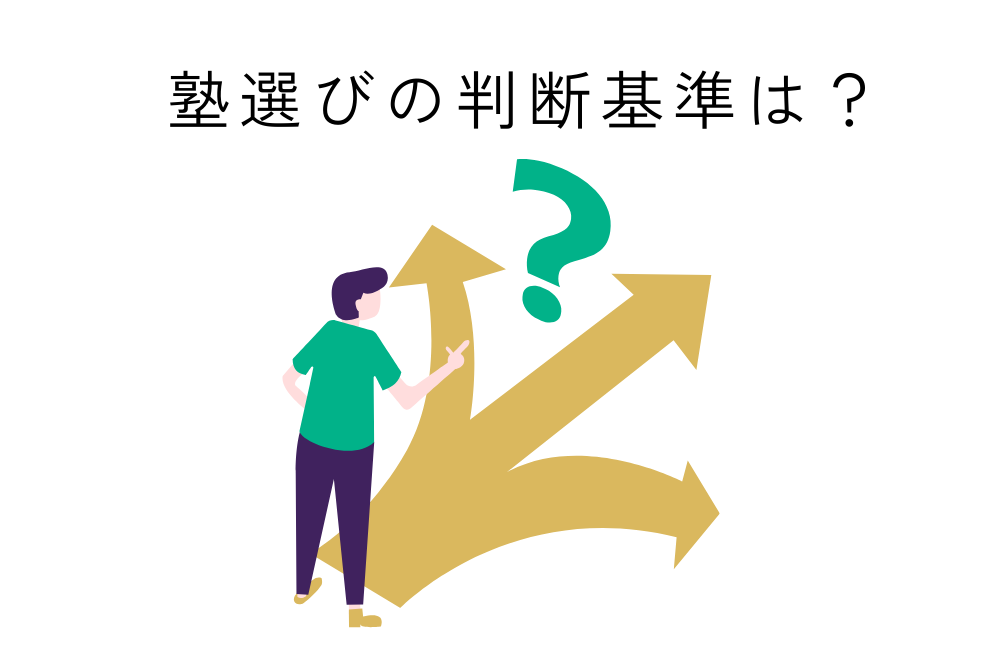
差分に基づいて「塾のタイプ」を決めたら、次は現実的な条件で具体的に塾の選択をしていきます。
どんなに評判の良い塾でも、距離的に通えなかったり予算が合わなければ継続できませんからね。
塾選びをする際には、最低限以下の3つの基準を確認することをおすすめします。
①通塾できる距離・時間か?
受験勉強は長期戦です。
通学時間が長すぎると、その分だけ宿題や復習に充てる時間が削られてしまいます。
一般的には片道45分〜1時間以内が目安です。
特に、中学受験のお子さんの場合や、女子生徒の場合の場合は、夜遅くなる帰宅時の安全面は必ずチェックするようにしましょう。
また、部活動や習い事と両立する場合は「週あたりの移動総量」で考えることも大切です。
例えば週3回通塾で片道40分なら、1週間に約4時間が移動に消えます。
この時間をどう活用できるかも含めて判断しましょう。
②費用は予算内に収まるか?
塾にかかる費用は月謝以外にも多くの項目があります。
入会前に必ず見積もりをもらい、年間トータルを試算しておきましょう。
- 月謝(授業料)
- 教材費
- 模試代
- 季節講習費(春・夏・冬)
- 合宿・特訓費用
- 交通費
特に季節講習費は月謝の2〜3倍になることも珍しくありません。
年間の合計額で無理がないかを確認することが重要です。
特に集団塾の場合は、利用者側で料金を調整することが難しいです。
最初に、しっかり試算しておくことが大事です。
逆に、個別指導塾や家庭教師は授業数や講師によって費用が跳ねやすく単価が高くなりがちですが、利用者側で予算の調整がしやすいです。
③お子さんの学年に対応しているか?
塾によっては学年ごとにカリキュラムの厚みが大きく異なります。
中学受験では小4~小5、高校受験では中2~中3が授業内容のギアが一段上がる時期です。
このタイミングで塾に入ると授業についていきやすい一方、遅れるとキャッチアップが大変になることもあります。
また、学年によって募集停止(満席)になっていることもありますので、早めの情報収集と体験授業の申し込みが必要です。
大学受験対応の塾は、高校受験対応の塾に比べ、実はとても少ないです。
高校受験の場合、大学生講師が教えることができますが、大学受験の場合、一部の非常に学力の高い大学生講師かプロ講師でないと教えるのが結構厳しい。
大学受験の予備校・塾はしっかり検討する必要があります。
④その他の確認ポイント
その他にも以下の点を確認しておきましょう。
- カリキュラムの柔軟性:志望校別クラスがあるか、苦手科目に対応できるか
- 講師の固定度:担当が頻繁に変わらないか(特に個別・家庭教師)
- 補習や欠席対応:振替授業や動画配信などのフォロー体制
- 保護者面談:進路相談・学習報告が定期的にあるか
これらを総合的に確認した上で、最終的に「お子さんが安心して通えるか」を一番の判断基準にしてください。
どれほど実績のある塾でも、お子さんが嫌々通っていては力を発揮できません。
性格や生活リズムに合った塾を選ぶことが、最終的な成果につながります。
“条件”と“相性”の両方が揃って初めて、塾選びは成功といえますね。
体験授業・面談で確認すべきポイント
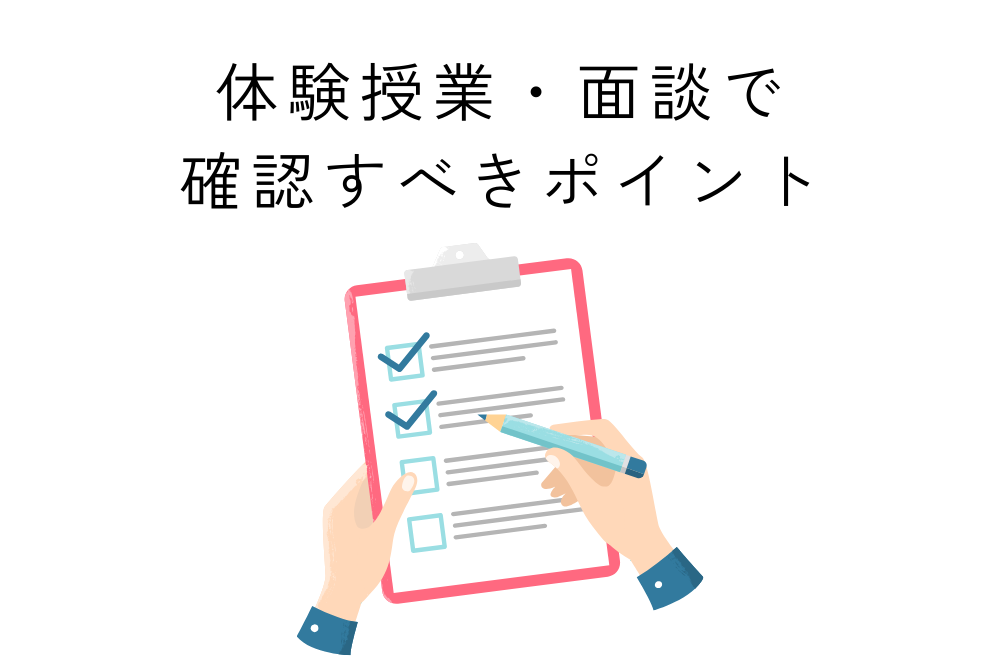
塾を最終的に決める前に、必ず体験授業や面談に参加しましょう。
パンフレットや口コミだけでは分からない“リアルな相性”を確認できるのはこのタイミングだけです。
ここでの見極めが、入塾後の成績伸びやモチベーションに直結します。
具体的に確認しておきたいポイントを整理すると、以下のようになります。
①授業の分かりやすさ・雰囲気
教室、講師の雰囲気はモチベーションに直結する大切な確認事項です。
- 先生の説明は論理的で分かりやすいか?
- 板書やプリントは整理されているか?
- 授業の雰囲気は集中できる環境か?
なかなか踏み込んだところまでは分からないと思いますが、できる限り感じ取るようにしましょう。
②宿題・課題の出し方
これは無料体験では分かりませんが、面談の際に確認してみましょう。
- 宿題の量は現実的か?
- 課題に優先順位が付けられているか?
- やるべきことが明確に示されているか?
この項目は、細かい部分まで確認できないと思いますが、できれば確認したいですね。
③フィードバック・面談の質
- 模試やテスト結果について、具体的な改善策を提示してくれるか?
- 保護者面談での説明は具体的で分かりやすいか?
- 進路相談の際に「次に何をすべきか」が明確になるか?
これは面談で確認できますね。
④講師や指導スタイルの安定性
- 担当講師は固定か?頻繁に変わらないか?
- 質問対応は授業外でもしやすい環境か?
これも面談で確認できる項目です。聞いておきましょう。
⑤サポート体制
- 欠席した場合のフォローはあるか?(振替授業・動画配信など)
- 自習室は利用できるか?雰囲気は集中できるか?
- 質問対応や追加課題の柔軟性はあるか?
利用し始めたら特に重要になる項目ですね。必ず確認しておきましょう。
これらのポイントを体験授業や面談で確認すれば、パンフレットや広告だけでは分からない“リアルな塾像”が見えてきます。
特に、「この塾なら頑張れる!」というお子さん自身の感触は最重要です。
親の判断だけでなく、本人の気持ちを尊重することが合格への近道となります。
体験授業や面談の際には、事前に質問をメモして持参するのもおすすめです。
印象に残った答えや反応をその場でメモしておくことで、後から複数塾を比較する際に役立ちます。
最後に
この記事では、受験の準備を始めようと思った時「まずは仮でもイイので目標を決める」ということ、その上で、塾の選び方まで具体的に解説しました。
受験勉強を始めるとき、多くのご家庭は「まず塾探し」と考えがちです。
しかし本当に大切なのは、志望校を仮にでも決め、その目標との差分を把握することです。
そのための第一歩が、私学フェスタや合同学校説明会に参加することです。
ここで「行きたい!」と思える学校に出会うことで、勉強の方向性と必要な努力の量が明確になります。
現在の自分の実力と目標との差分を埋めるために塾や勉強方法を選んでいくのが、もっとも論理的で効率の良い受験戦略です。
塾を選ぶ際には、差分の大きさと残された時間を基準にタイプを判断し、さらに距離・費用・学年対応といった現実的な条件を確認してください。
そして最終判断は、体験授業や面談での感触をもとに、お子さんが「ここなら頑張れる!」と感じられる塾を選ぶことが重要です。
受験は親子にとって長い道のりですが、最初の一歩を間違えなければ、その後の道すじはぐっと明確になります。
さあ、まずは私学フェスタ・合同学校説明会に足を運び、未来への一歩を踏み出してみましょう。